はじめに

限られた時間の使い方
朝、時計と競争するようにご飯を食べさせ、洗濯機を回し、ゴミを出し、子どもを学校へ送り出す。ホッと一息つく間もなく、今度は自分の仕事へ。
夕方、急いでスーパーに寄り、学童や保育園にお迎え。帰宅したら、休む間もなく夕飯の支度、お風呂、宿題チェック、明日の準備。気づけばもう寝る時間。
「今日も一日が終わった。明日は…」
そんな、息つく暇もないような毎日を送っているお母さん、お父さん、本当にお疲れ様です。
平日は仕事と家事、育児のルーティンで手一杯。子どもとゆっくり向き合えるのは、週末くらいという方も多いのではないでしょうか?
ですが、子どもの成長はあっという間。だからこそ、限られた時間の中でどうお子さんと関わっていくかは常に悩ましいテーマですよね。
子どもの可能性をどう伸ばすか
実は私にも今年8歳になる息子がいまして、子どもとの向き合い方を考えて色んな本やネットの情報を読み漁ったところ、私たちが子育てをしている小学生(6歳~12歳頃)は、
具体的な物事を論理的に考えられるようになる「具体的操作期」から、抽象的な思考や仮説検証能力が伸びる「形式的操作期」へと移行していく、非常に重要な時期なんだそうです。
「急に何を言い出したの?」と思う人もいれば、「知ってる知ってる」という人もいるかと思いますが、これは発達心理学という学問で出てくる言葉です。
この時期の子どもは、好奇心も旺盛になり、「なんで?」「どうして?」が加速する一方で、友達との関係や自分の興味関心もどんどん広がっていきますよね。
そんな中で、ふと子どもが目を輝かせて「これ、やってみたい!」「このおもちゃ、すごく面白そう!」と言ってくる瞬間、ありませんか?
特に、それが学びや創造性を刺激しそうなものだったりすると、やらせてあげたい。この子の可能性を伸ばしてあげたい。と思うのが親心ですよね。
ですが、同時に現実的な悩みもあると思います。
現実的な悩み
「ちゃんと続けられるかな?」「家計的に費用はどう?」「すぐ飽きちゃうんじゃない?」「親のサポートはどれくらい必要?」といった悩みもあると思いますし、
子どもの「やりたい!」という気持ち、つまり内発的な動機は大切にしたいけど、何でも買い与えることが本当に子どものためになるのか?
衝動性をコントロールする力や、物の価値を理解することも学んでほしいから、むしろすぐに買い与えないほうが子どもにとっては良いんじゃないか?
といった葛藤もあるかと思います。とても悩ましいですが、これらは子どもの金銭教育や社会性を育む上でも避けて通れない課題ですよね。
そこで今回は、私たち親が子どもの欲求にどう向き合っていくのがより良いのか、忙しい毎日の中でもできることはないか、深く掘り下げて考えてみたいと思います。
心理学から見る3つの購入方法
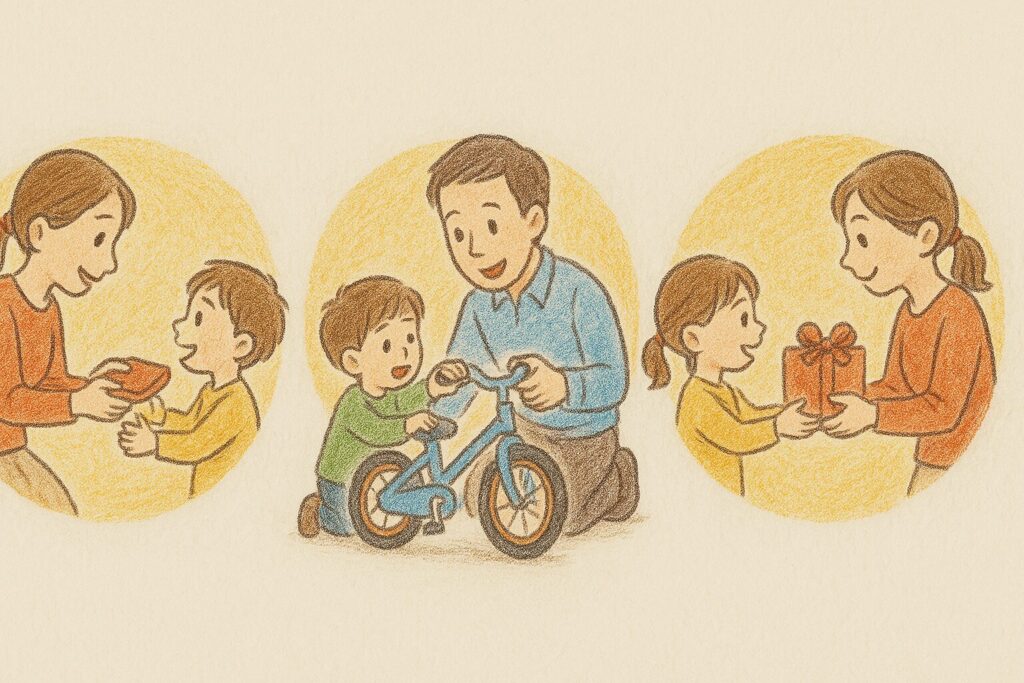
子どもの「やりたい!」という熱意、特にそれが学びにつながりそうなものだと、親としては全力で応援したくなりますよね。
では、それを買う理想的なタイミングなんてあるんでしょうか?
ここでは、このサイトで取り扱っているクランチラボのような学習教材を例に、それぞれの心理学的な意味合いや発達への影響も考慮しながら、メリット・デメリットを見ていきます。
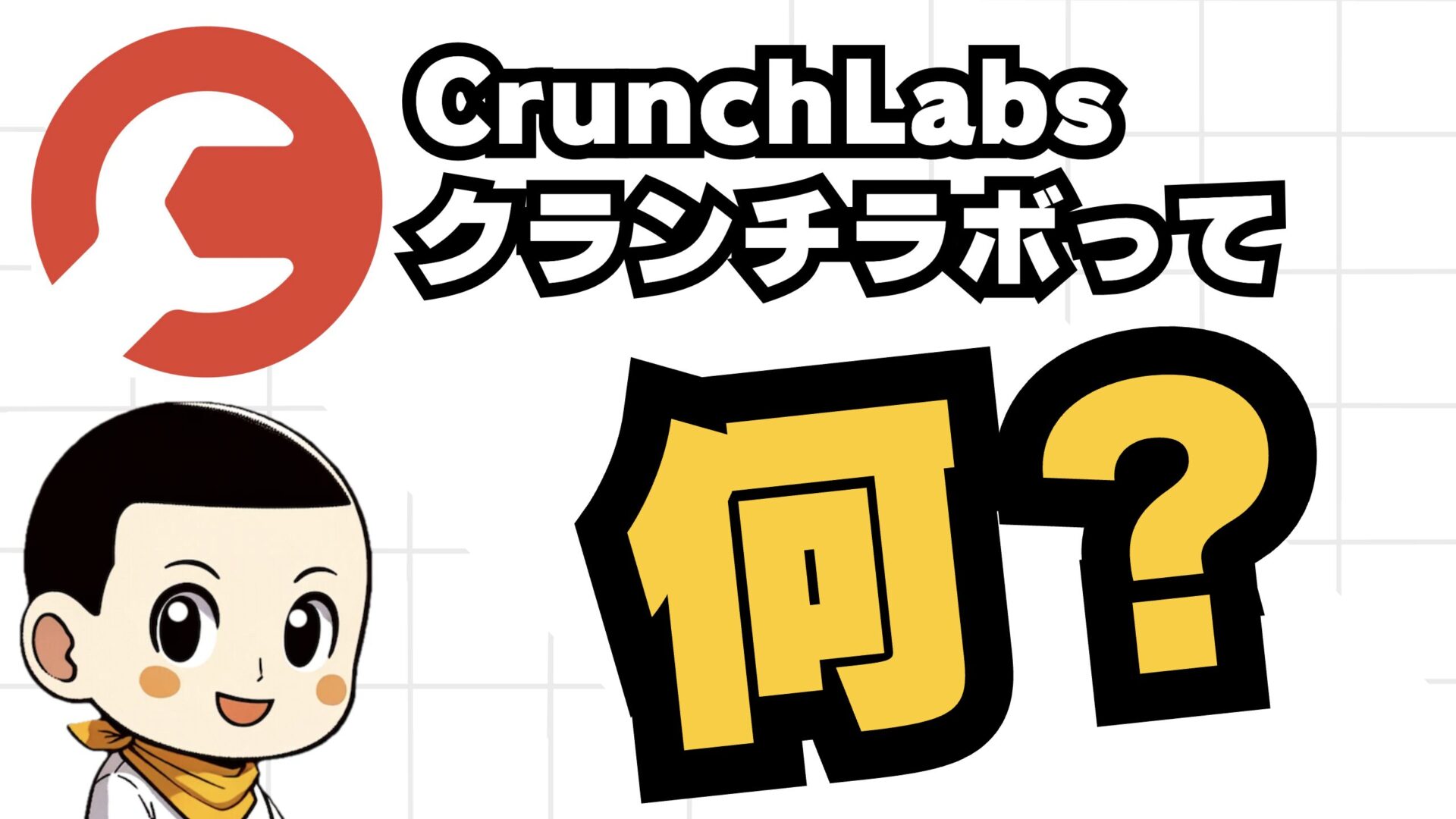
選択肢1:即購入する
子どもが「欲しい!やりたい!」と目を輝かせたその瞬間に、「よし、わかった!挑戦してみよう!」とすぐに環境を整えるパターンです。
即購入するというのは、日本にある鉄は熱いうちに打てという格言のとおり、内発的な動機が湧いた瞬間こそが最も適した時期だという考え方ですね。
心理学的なメリット
●内発的動機づけの尊重と強化:
自己決定理論によれば、人間は「自律性(自分で選びたい)」「有能感(できるようになりたい)」「関係性(人と繋がりたい)」という基本的な心理欲求を持っています。
子どもの「やりたい!」にすぐ応えることは、まさにこの「自律性」の欲求を満たし、自分から「知りたい」「学びたい」と思う内発的動機づけを強く刺激します。興味が最高潮の時に始められるため、学習効果も高まりやすいと考えられます。
●「学習=楽しい」体験の獲得:
特にクランチラボのような遊びを通して学ぶ教材は、学習に対するポジティブな感情(面白い、ワクワクする)を育みます。これは、将来の学習意欲にも良い影響を与える可能性があります。
●自己肯定感と親子の信頼関係:
自分の興味関心を親に認められ、すぐに応えてもらえた経験は、「自分は大切な存在だ」「親は自分の気持ちを理解してくれる」という感覚、すなわち自己肯定感やアタッチメント(愛着)の安定に繋がります。
心理学的なデメリット・注意点
●欲求の遅延耐性の発達機会損失:
欲しいものがすぐに手に入る経験が続くと、自分の欲求をコントロールし、目標のために一時的な満足を我慢する力、いわゆる欲求の遅延耐性を育む機会が少なくなる可能性があります。
この能力は、衝動性のコントロールや将来の計画性にも関連すると言われています。
●興味の移ろいやすさへの対応:
発達心理学的に見ても、小学生、特に低学年のうちは興味の対象が移ろいやすい時期です。高価な教材をすぐに与えたものの、すぐに飽きてしまった場合、子ども自身も「飽きっぽい自分はダメだ」と感じてしまう可能性も。
●「有能感」が満たされないリスク:
もし、キットが難しすぎて親のサポートなしでは進められず、結果的に「できなかった」という経験ばかりになると、自己決定理論でいう「有能感」が満たされず、逆効果になる可能性もあります。
選択肢2:熟考してから決める
「クランチラボ、面白そうだね! でも、すぐに決めるんじゃなくて、本当に続けられそうか、少し考えてみようか」と、一定期間を置いたり条件を設けたりするパターンです。
心理学的なメリット:
欲求の遅延耐性と自己制御の育成:
このパターンの最大のメリットは、前述の欲求の遅延耐性を育む機会となる点です。すぐには手に入らない状況の中で、自分の欲しい!という衝動と向き合い、コントロールすることを学びます。
これは、発達心理学で重要視される自己調整能力の発達に繋がります。
目標設定と計画性の練習:
「次の誕生日まで待つ」「お小遣いをいくら貯めたら考える」といった条件を設定することで、目標達成に向けた具体的な計画を立て、実行する練習になります。これは子どもの金銭教育の観点からも有効です。
対象への価値認識の向上:
待つ時間や努力があったからこそ、手に入れた時の喜びは大きくなり、その教材に対する価値を感じ、大切に扱おうとする気持ちが芽生える可能性があります。
心理学的なデメリット・注意点
内発的動機づけの減退リスク:
最も懸念されるのは、待っている間に興味関心のピークが過ぎてしまい、せっかくの「やりたい!」という内発的動機づけが失われてしまうことです。タイミングの見極めが非常に重要になります。
「有能感」「関係性」の阻害:
子どもが「どうせ言っても無駄だ」「親は自分の気持ちを分かってくれない」と感じてしまうと、自己決定理論における「有能感」(自分にはできる、という感覚)や「関係性」(親との繋がり)が損なわれ、
自己表現をためらったり、親への不信感を抱いたりする可能性も否定できません。
単なる「我慢」で終わらせない工夫:
ただ待たせるだけでなく、なぜ待つのか、いつまで待つのかを明確に伝え、その間も関連する本を読んだり、別の簡単な工作をしたりするなど、興味を繋ぎ止める工夫が必要です。
選択肢3:自力で買わせる
「クランチラボ、やりたいなら自分でお金を貯めてみたらどうかな?」と、子ども自身の努力によって購入資金(の全部または一部)を子どもに用意させるパターンです。
心理学的なメリット:
自己効力感の育成(買えた場合):
心理学者バンデューラが提唱した自己効力感、つまり「自分ならできる!」という自信は、目標を設定し、努力し、それを達成する経験を通して育まれます。もし子どもが自力で目標を達成できれば、それは大きな自信となるでしょう。
金銭感覚と労働観の学習:
お金の価値、計画的な貯蓄、労働(お手伝いなど)とその対価について具体的に学ぶ機会となり、子どもの金銭教育として有効な側面もあります。
心理学的なデメリット・注意点
発達段階に合わない過度な要求:
発達心理学的に見て、小学生、特に低学年にとって、クランチラボのような比較的高価なサブスクリプション費用を全額自力で賄うのは非現実的な目標設定と言えます。
達成困難な目標は、自己効力感を育むどころか、「自分には無理だ」という無力感を学習させてしまうリスクがあります(学習性無力感と言います)。
機会の不平等と学習機会の損失:
家庭の経済状況や、子どもがお金を稼ぐ機会には差があります。これを主な方法とすると、「お金がある家の子は学べるけど、うちは学べない」という状況を生み出し、子どもの学習機会を奪うことになりかねません。
外発的動機づけへの偏り:
本来、学びは知的好奇心という内発的動機づけに基づくのが理想ですが、「お金のために学ぶ」「お金がないと学べない」という意識が強まると、外発的動機づけ(外からの要因に)に偏り、学びの本質的な喜びが見失われる可能性があります。
したがって、この自力パターンは、学習教材に対して全面的に適用するのは慎重になるべきで、あくまで補助的な要素として、子どもの年齢や状況に合わせて無理のない範囲で取り入れるのが現実的でしょう。
結局どれがいいの?
ここまで3つの購入パターンとその心理学的な意味合いを見てきましたが、即購入も、熟考も、自力・・・はちょっと金額によっては難しそうですが、それぞれにメリット・デメリットがあり、「結局、どれが一番良いの?」と迷ってしまいますよね。
この手の話を本やネットの情報で見ると、多くの専門家や育児書が最終的に「その子に合った方法を探しましょう」と結論づけることが多いと思います。
実際、子どもの発達段階、性格、興味の対象、そして何より家庭ごとの状況(時間、お金、親の考え方など)が千差万別なため、誰にでも当てはまる万能の正解は残念ながらありませんから、そう結論づけるのも分からなくはないです。
ただ、「結局、その子に合った方法を探しましょう」と言われても、「それが分かれば苦労しないよ!」というのが本音ではないでしょうか。特に、忙しい毎日の中では、じっくり観察したり、他の選択肢を比較検討したりする時間もなかなか取れないかもしれません。
そこで私がおすすめするのは、正解ではなく「納得解」です。
納得解とは?
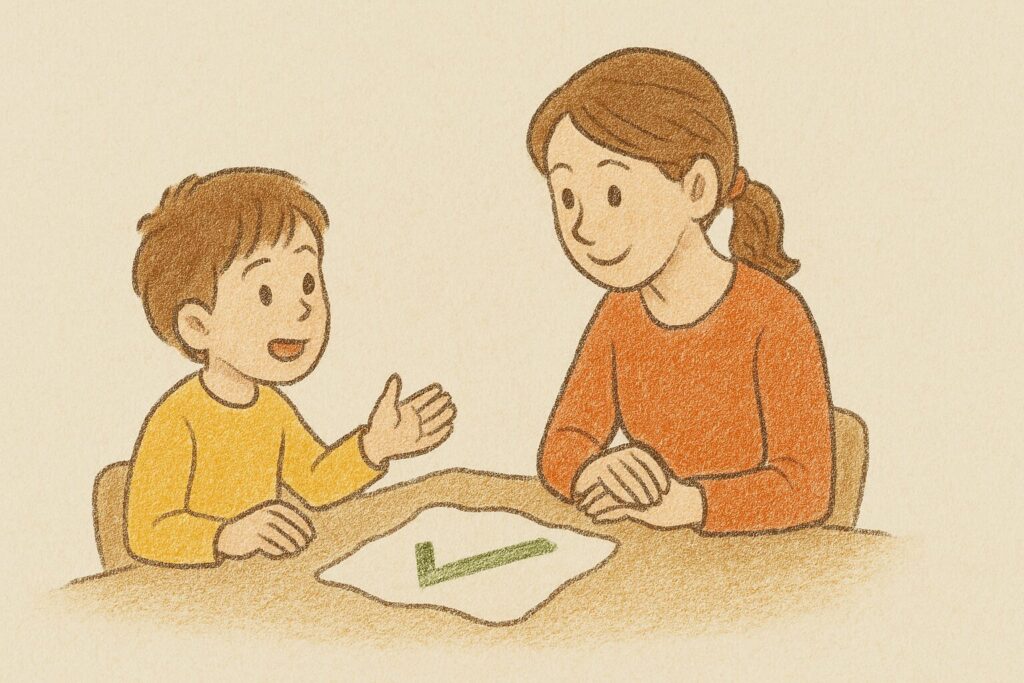
「正解」よりも「納得解」
ここでいう「納得解」とは、親子が共に「これでいこう」と納得できる答えのことです。
それは必ずしも正解だったり、最も効率的な最適解ではないかもしれませんが、家族だからこそ、お互いの気持ちを尊重し合える着地点があっても良いのではないでしょうか。
特に、心も成長段階の子どもにとっては、頭ごなしの正論よりも、自分の気持ちを受け止めてもらった上での結論の方が心に響き、次へのエネルギーになることも多いはずです。
では、その納得解を見つけるためのヒントを考えてみたいと思います。
1.子どもの「なぜ?」を深掘り:
「欲しい!」という言葉の裏にある理由を探ってみましょう。「クランチラボの何が面白そう?」「どんなことをしてみたい?」と具体的に聞くことで、一時的な衝動なのか、本当に強い興味関心なのかが見えてくることがあります。
この対話自体が、子どもが自分の気持ちを整理し、言葉にする練習にもなりますし、親も子どもの興味の方向性をより深く理解できます。
2.「お試し」の機会を探る:
いきなり高価なものや長期契約(サブスクなど)に踏み切る前に、似たような体験ができる安価なキットや、図書館の本、地域のワークショップなどを探してみるのも一つの手です。
クランチラボのようなサブスクの場合、単発購入や中古品は現状なさそうですが、公式サイトの動画を見たり、類似の工作キットで「作る楽しさ」自体を試したりすることはできるかもしれません。
3.「条件」をゲーム感覚で設定:
もし「熟考」や「自力」の要素を取り入れるなら、一方的に我慢させるのではなく、親子で納得できる「ルール」を決めるのがおすすめです。
例えば、「1ヶ月、クランチラボのサイトを見て本当にやりたい気持ちが変わらなかったら考えよう」「お小遣いの一部(例えば500円)を自分で貯めたら、残りは出してあげる」など、子どもでも達成可能な目標を設定することで、子どものモチベーションを維持しつつ、計画性や金銭感覚を養うきっかけにもなります。
4.親自身の「軸」を意識する:
私たち親自身が、子育てにおいて何を大切にしたいのか。知的好奇心を最優先したいのか、計画性なのか、物の大切さなのかを、改めて考えてみることも重要です。
その軸が明確になれば、日々の小さな選択にも一貫性が生まれ、迷いが少なくなります。もちろん、状況によって優先順位が変わることはありますが、自分なりの判断基準を持つことが、納得感に繋がります。
これらのヒントは、どれか一つを選ぶというより、子どもの年齢や性格、家庭の状況に合わせて柔軟に組み合わせることが大切です。
ちなみに、私の家は普段からこういう話をしているかといったら、全部ではありませんが、1と4はしますね。せっかくなので、事例として書いておきます。
我が家(筆者)の話
はじめに、我が家は夫婦と子どもが1人の3人家族です。子どもは小学2年生の男の子です。
子育てに限らず、時間を意識することは3人とも共通しているので、気に入らなかったら売れば良いという考えのもと、2や3について話すことは基本的にありません。
子どもの「欲しい!」に対しては、それが学習系のものだったらその場で本人に意思表示してもらって、「なぜ欲しいか」「どういうとこが気になっているか」を聞いたうえで、その年相応の説明ができていたら基本的に即購入というようにしています。
これが結構面白くて、保育園のときには「欲しいから欲しい!」という理由になっていない理由でもokしましたし笑 小学校に上がってすぐも「楽しそうだから欲しい」くらいでしたが、
一昨日クランチラボの契約をしたときは、「ものを作るのが好きだし、YouTubeを見ていて楽しそうだし、作った後も楽しいものが残るから欲しい」と、理由づけが増えてきました。こういうところからも子どもの成長を感じられて、楽しいですね。
あと、うちは2〜3年に1回程度ですが夫婦で子育てについて話す時間を設けており・・・「設けている」と書くと定期的に何時間も話し合っていそうに聞こえてしまいますが、実際には「今ちょっといい?」から急にはじまる数分の話し合いですね笑
その話し合いで、子育てで優先したいことについては毎回確認するようにしています。うちの場合、生後半年くらいに初めてこんな話をしたときから、
私は勇気。
妻は自信。
ということで、言葉は違えど方向性は似ていたので、最初から夫婦間で子育てで重視したいことが違わなかったのは良かったですね。
大切なのは購入後の「関わり方」
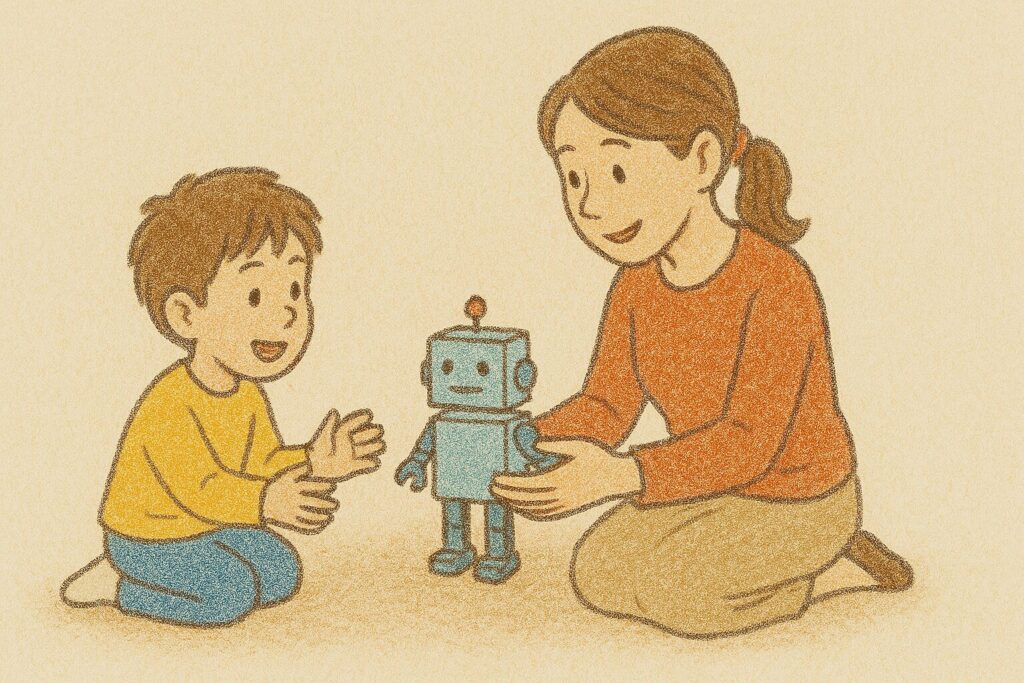
一緒に遊ぼう!
どの選択肢を選ぶにしても、忘れてはならないのが「買って終わり」にしないということです。
特にクランチラボのような教材は、子ども一人で完結するものではなく、親子で一緒に試行錯誤したり、「すごいね!」「こんな工夫ができるんだ!」とプロセスを認め、共感したりする関わりが、子どもの学びを深め、自己肯定感を育む上で非常に重要になります。
たとえ「即購入」したとしても、その後、親が全く関心を示さなければ、子どもの興味は長続きしないかもしれません。
逆に、「熟考」して手に入れたものなら、大切に使う気持ちが育ちやすいかもしれませんが、難しくて挫折しそうな時に親のサポートがなければ、「やっぱり自分には無理だ」と感じてしまう可能性もあります。
忙しい毎日の中で、常にべったり付き添うことは難しいかもしれません。それでも、「どう?進んでる?」「面白い発見あった?」と声をかける、「週末に一緒にやってみようか」と時間を作る、完成したものや頑張っている過程を写真に撮って褒めるなど、
ちょっとした関わりが、子どもの「やりたい!」という気持ちを支え、学びを豊かなものにしてくれます。
まとめ
子どもの「やりたい!」という輝く瞬間。それをどう受け止め、どう応えるか。この記事では、3つの購入パターンとその心理学的な意味合い、そして「納得解」を見つけるためのヒントについて探ってきました。
完璧な正解はありません。大切なのは子どもの気持ちに寄り添い、対話し、そして親自身も納得できる方法を焦らず探していくプロセスそのものだと思います。
限られた時間の中でも子どもと向き合い、その可能性を信じて関わることは、きっとできます。今日お伝えしたことが、少しでもそのヒントになれば幸いです。
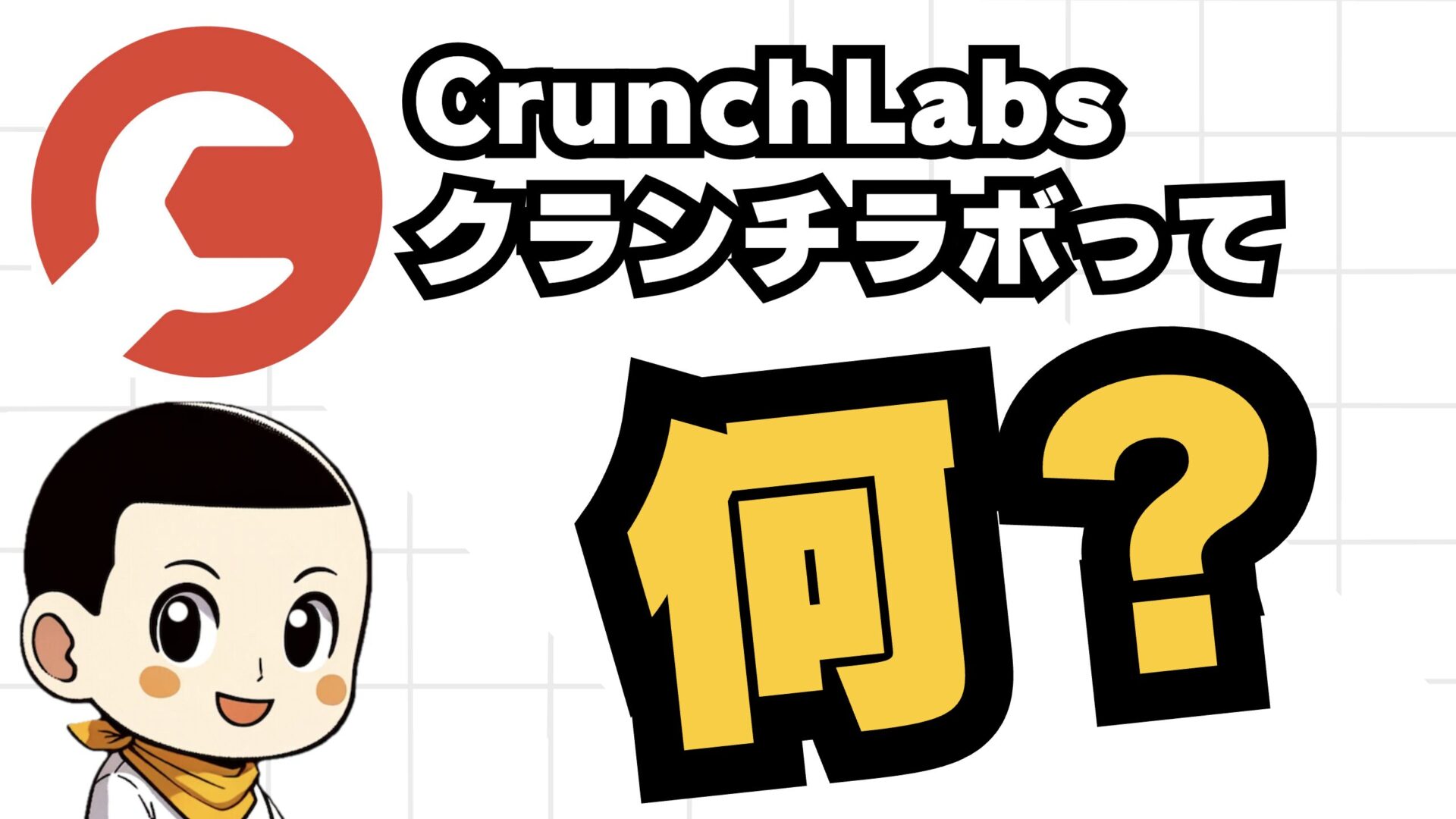
もし、何かのきっかけでこのページをご覧になった方は、是非クランチラボについても見ていってください。
サイト内検索できます
このサイトでは、クランチラボに関するあらゆる情報を掲載しています。
以下のトップページにある検索窓ではサイト内の全てのテキストを参照して検索できますので、気になっていた商品名や原理の名前などで検索してみてください!!
ぜひコメントをお願いします!
いつも最後までご覧いただき、本当にありがとうございます!
【コンプ図鑑】クランチラボ図鑑は個人で運営しているサイトです。あなたの感想やちょっとしたコメントが更新の支えになるため、一言いただけるととても嬉しいです。
このサイトについては、こちらの「はじめに」ページにまとめてあるので、サイトの方針や私について知りたいという方がいらしたら、こちらをご覧ください。
ご家族にシェアしてください!!
この投稿が面白いと思ったら、是非ご家族にシェアしてください!
なお、動画やブログ等で引用いただく際は無断でokですが、そのときは出典元として以下の名前とリンクの掲載をお願いします。
【コンプ図鑑】クランチラボ図鑑
https://completezukan.jp/CrunchLabs/
今後ともよろしくお願いします!!

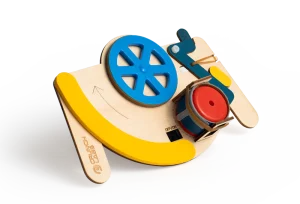

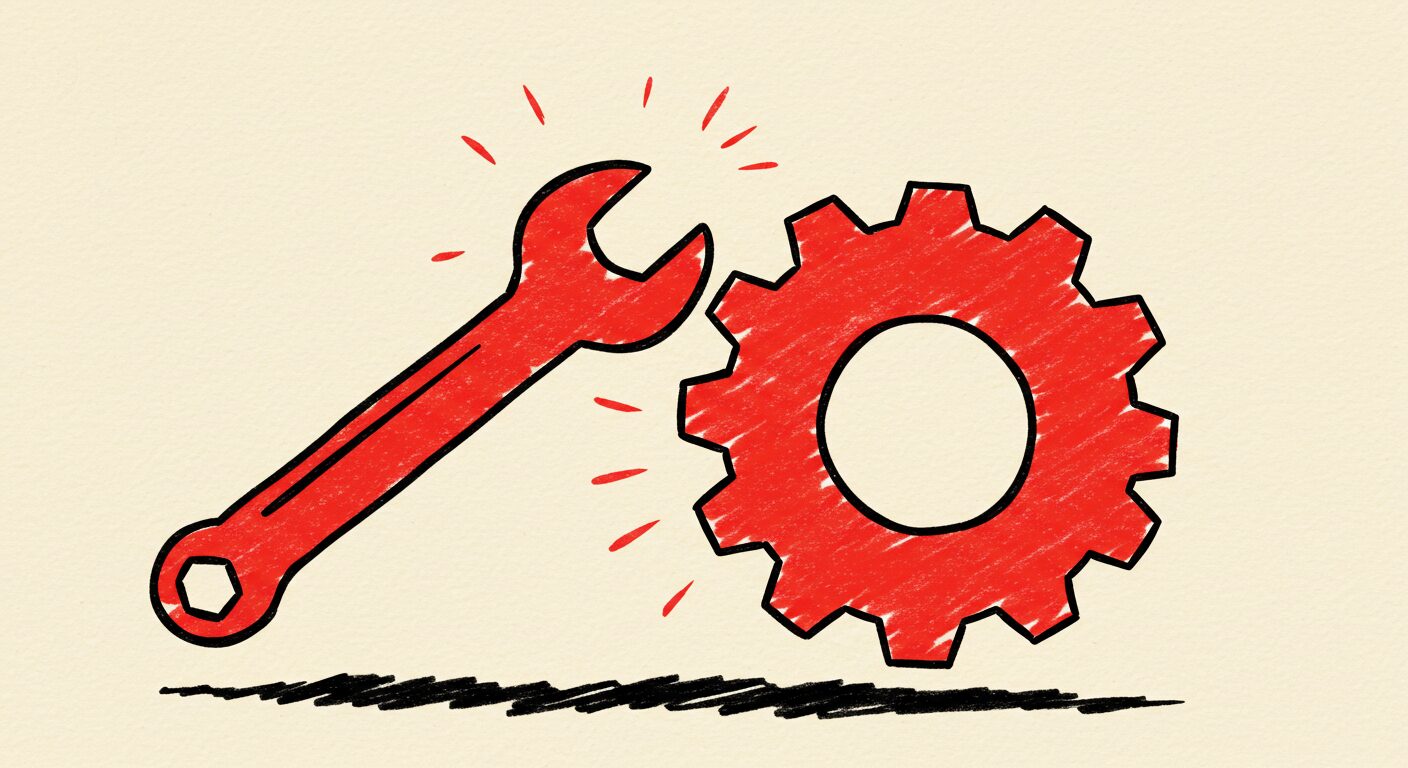



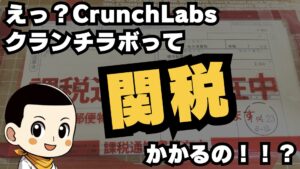
コメント ※スパム対策で承認制です